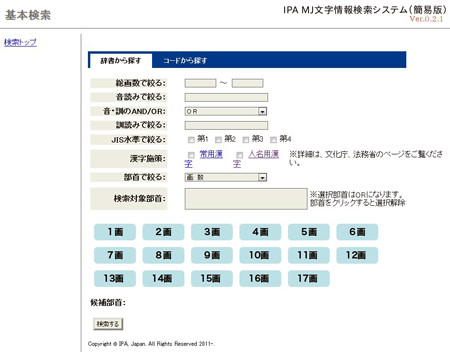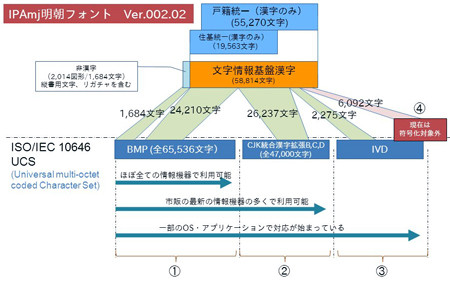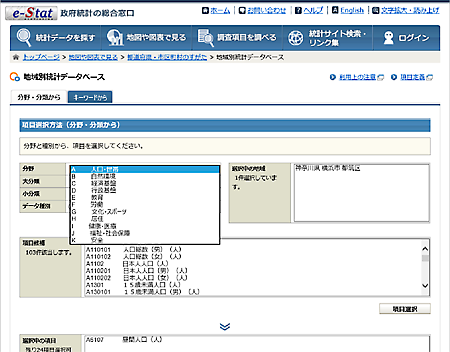システムサポート部の三好です。
最近ニュースを賑わせている「ビットコイン」。「インターネット上で流通している電子マネー」という認識くらいしか持っていない方がほとんどだと思います。そもそもビットコインって何?という疑問の前に、まず「お金」という概念についておさらいしましょう。
ご存知の通り、普段皆さんが利用している1万円札や500円玉そのものには価値がありません。1万円札はただの紙切れですし、500円玉はただの金属のかたまりです。そんなただの紙切れや金属のかたまりを支払うと、その対価としてモノやサービスを手に入れることができるのは、我々がその紙切れ・金属のかたまりを価値のあるものだと「思い込んでいる」共通認識があるからです。その「思い込み」=「信用」です。
では、なぜ多くの人がただの紙切れや金属のかたまりを信用できるのか?それは紙幣・貨幣を発行している国を信用しているからです。押さえておきたいポイントは、お金は「それに価値があるという共通の思い込み」があって成り立つということです。
ただ、いきなり通貨発行者(国)が、「この紙が今日から1万円の価値になるから、よろしく!」と言ったところで、人々(国民)が信用するはずがありません。国が人々から信用を得る以前は、希少価値のある「金(ゴールド)」を信用の担保としていました。いわゆる兌換(だかん)紙幣(同額の金貨に交換することを約束した紙幣)という仕組みですね。紙切れを持っていけばいつでも希少価値のある金と交換できるので「この紙に1万円の価値がある」と信用できたわけです。※現代では国の信用と引き換えに通貨を発行する、不換紙幣(金貨との交換を保証しない紙幣)が流通しています。
さて、今回の話題のメインテーマであるビットコイン。ビットコインのシステムには国や政府といった通貨の信用を裏付けする役割を果たす機関が存在しません。通貨を使用する人々が、国のような信用する先を持たないビットコインをなぜ貨幣として信用し、「価値」を見出しているのでしょうか?
ビットコインの「価値」の話に移る前に、日本円をドルに交換するのは何故か?ということから考えてみましょう。当たり前ですが、円のままだと買えないモノがあるから交換しますよね?ビットコインに価値がつくのもまさにこの点なのです。例えばアメリカの商品が欲しいと思った場合、円では対応していないところがあります。この場合、円をドルに交換して商品を手に入れることになりますが、この為替の交換手数料、並びに海外への送金手数料というのが非常に高額で、小さい物を買う場合には商品代金<手数料となることも少なくありません。
そこでビットコインが登場するわけです。ビットコインは銀行を通す必要が無いので両替の手数料が1%掛かる程度で送金手数料などはかかりません。つまり、他の外国為替に両替して送金するよりも格段に安くつくので使い勝手が良いわけです。国内で物を売買する人にはあまり旨味はありませんが、海外取引をする人には非常に有益な為替に近いものなんですね。つまり、「ビットコイン自身」にというよりは、「ビットコインの流通のメリット」に価値が見出されたというわけです。
日本人はアメリカ人と取引をする為に円でビットコインを買う。アメリカ人はユーロ諸国と取引をする為にドルでビットコインを買う。中国人は色んな国と取引をするために元でビットコインを買う。そうしていくと、各国でビットコイン高自国通貨安という普通の為替と同じような価値基準が生まれ、全世界に流通していきます。
最初はごくごく一部の人たちの間だけで流通していた内輪のいわゆる「アングラ」なマネーであったビットコインですが、物珍しさと利便性に惹かれて徐々に色んな人達が注目し始め、その期待が加熱し、徐々に価値が上がっていきます。
極めつけは2013年のギリシャ財政破綻。「国が発行しているお金すら信用できない!」と考えた人たちがビットコインという仮想通貨へ投資を始めることになり一気に価値が上昇しました。(約1000倍!)
また、メディアが煽ることにより「ビットコインって価値がありそうだよね…」と多くの人々が思い込みはじめました。先述したように共通認識として「価値がある」と思い込んでいる(信用している)人たちの間でビットコインは相応の通貨として機能していったわけです。
さて、そんな人気の仮想通貨の取引所であった「マウントゴックス社(MtGox)」がサイバー攻撃を受けてシステムがダウンし、ビットコイン取引やサーバーに保管しておいた顧客のビットコインが消えてしまった、というのがここ最近のニュースです。
テレビのインタビューで、ある投資家が「リスクがあることはわかっていたのでコインが消えても怒ってないよ」と言っていました。ビットコインは投資と同じなので、リスクがあるのは他の投資と同じです。いつかビットコインの価値が0になることも十分考えられる、それをわかってビットコインを持っていたから問題ない。ということですかね。
投資家の方がおっしゃっていた「リスク」に「取引所がつぶれる」というリスクが含まれていたかは定かではありません・・・株の世界だと日経取引所がつぶれることに近いわけですから。
今回の問題の責任の所在は?というのが一番の問題。ビットコインは誰が発行しているわけでもないものです。民事再生法を申請したMtGox社は、そのコインを取引している会社で、コイン発行会社でも管理会社でもありません。麻生太郎財務相が「通貨として誰も認めていない。長く続かないと思っていた。どこかで破綻すると思っていた」と被害者の自己責任と言っています。簡単にクラッキングされるような脆弱なページを作ったことは責任追及されるかもしれないですが、ビットコインの取引をしている会社が(管理が悪くて)ビットコインを失った、というのは今の法律ではどういう風に解釈され、どう処分が下るのでしょう?なかなか興味深い所です。
今回の件をきっかけに仮想通貨の問題がたくさん取り上げられ、あまりよくないイメージがついてしまったのは少し残念な気がします。仮想通貨には海外取引・国際送金を含め、いい所がたくさんあります。通貨を発行している国としては認めづらいと思いますし、匿名性の高さによる資金洗浄などの悪用、責任の所在が不明瞭など問題点も多くありますが、これを機会に安全に仮想通貨を扱えるような法整備が進んでいけばいいなと思います。