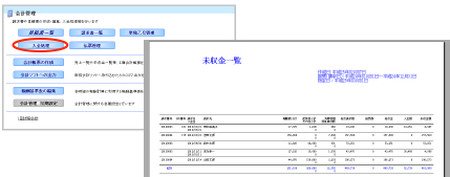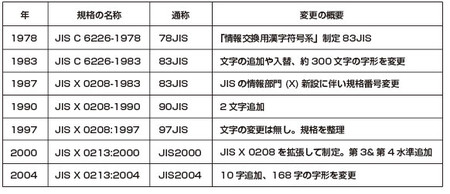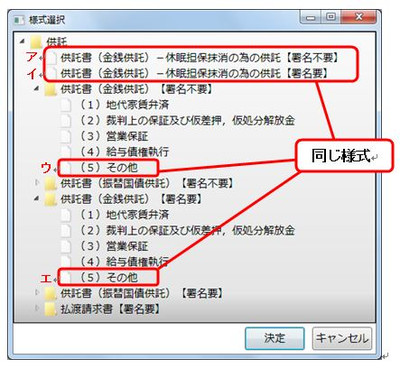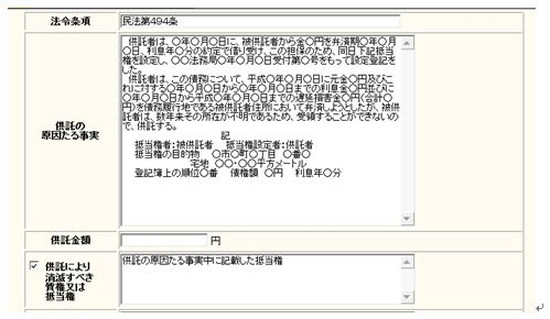タブレットについて
私事で恐縮ですが、昨年の10月頃、家族が誕生日にGoogleのタブレットNexus7をプレゼントしてくれました。

恥ずかしながら、毎月の通信料が上がるのがイヤで、携帯ガジェットには疎かったのですが、最初はおっかなびっくり使い始め、今では手放せないツールになっています。実際に生活の中で利用するようになって以来、デスクトップ/ノートPCを利用したデータ処理にいかに無駄があったかを実感しています。
ソフトウェア機能のバリエーションや、処理するデータのサイズ、入力支援の多様さなどは、強力なPCリソースをフルに利用可能で、これまでソフトウェア資源の蓄積があるデスクトップPCに一日の長があります。
しかし、キーワードを検索・表示して内容を読むなど、データを閲覧する機能については、携帯ガジェットでも必要十分なパワーがありますし、画面を見やすい場所に置く、表示を変更するなどの小回りがきき、利用時に機材の設置場所まで足を運ぶ必要がない(これは盲点でした)。必要なとき、たとえば友人との会話中でも、わからないことをネットで参照して確認できる、というアクセスの簡便さは得がたいものです。
おそらく、これからしばらくの間は、情報を検索、閲覧、確認する場合はウェアラブルな携帯端末で、文書を作成・加工するなど、データを大量に作成する場合は、入力しやすく、またセキュリティが確保された機材で、というように棲み分けが行われていくのでしょう。
さて、Windowsの電源を入れ、弊社のソフトウェアを立ちあげてからの効率アップ、無駄の削減については、これまで社の内外を問わずさまざまなご意見を頂き、少しずつではありますが、改善に取り組んで参りました。
しかしながら、近年、デバイス自体も、ネットの利用形態も多様化し、Windows自体もバージョン8からモバイルユース、ライトユースへの大幅な転換を行いつつあります。Windowsに限らず、目的や利用シーンに応じたデバイスを再度検討し直し、現在のサービスを分解・再構成して、ピンポイントで役に立つサービスを提供していくアプローチが必要なのではないか、と感じています。
もちろん、セキュリティの問題、利用形態の問題、デバイスの価格や管理の問題、実際の人力作業コストなどなど、様々なハードルがあることは承知しておりますが、サービスの品質はそのままに、より自由度と利便性を高めた商品を提供できるよう努めて参りたいと考えております。
引き続き、皆様のご意見・ご要望を頂戴できれば幸いに存じます。
今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。