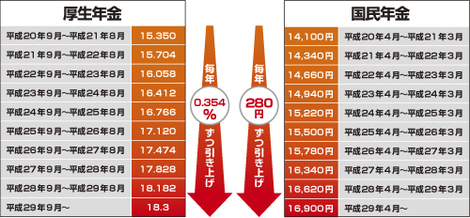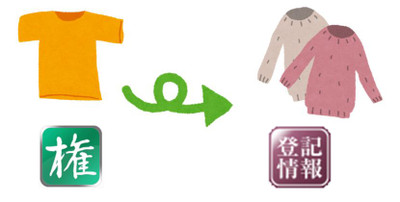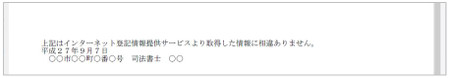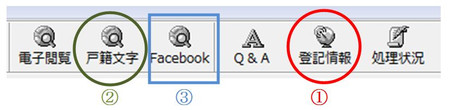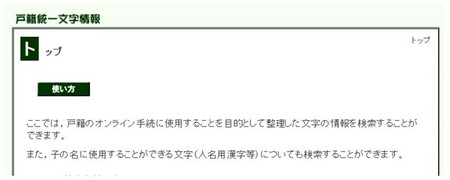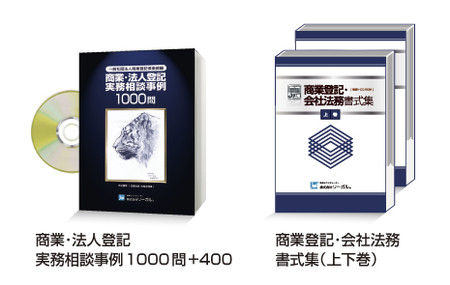コンセントの周波数
開発部の万場です。
今回は私が引っ越しをした際に気になったお話しをさせていただきます。
日本のコンセントは東と西で周波数が違っています。東日本での交流送電は1893年に電力会社が50Hzのドイツ製発電機を導入して始まりました。それまで使用していた直流送電に比べて効率がよく安定した送電が可能になりましたが、東日本が50Hzを導入した時点で西日本の電力会社は既に60Hzのアメリカ製発電機を使用していたことにより東西で周波数が分かれました。

私は昨年東京都からリーガル本社のある愛媛県に引っ越す事になり、引っ越し当日に大爆発を起こしては近隣の方々にご迷惑ですので周波数が違って使えるもの、使えないものを調べてみました。
そのまま使えるもの(電熱を利用する機器)
・白熱電球
・トースター
など
使えるが能力が変わるもの(モータを利用する機器)
・扇風機
・換気扇
・掃除機
など
使えないもの※両対応と書いてあるもの以外(周波数を利用する機器)
・洗濯機
・蛍光灯
・電子レンジ
など
携帯電話、ノートパソコン等の充電器は大半が100V~240Vで両方の周波数に対応しており世界中で同じものを利用できるようになっています。出張、旅行など持ち歩く機会の多いものなのでとても便利ですね。