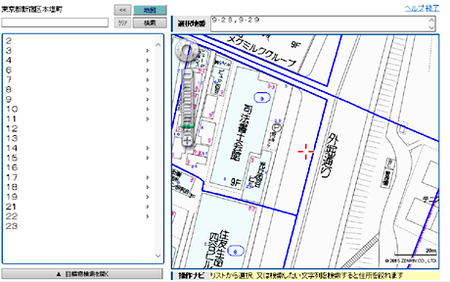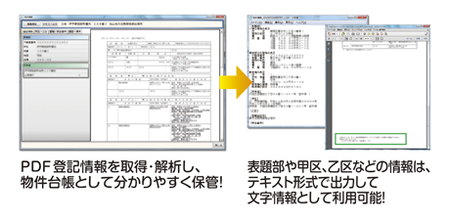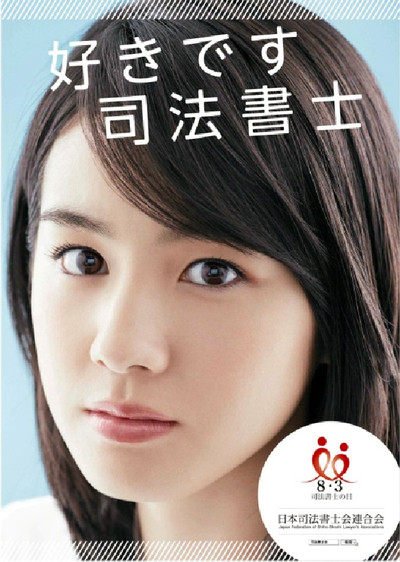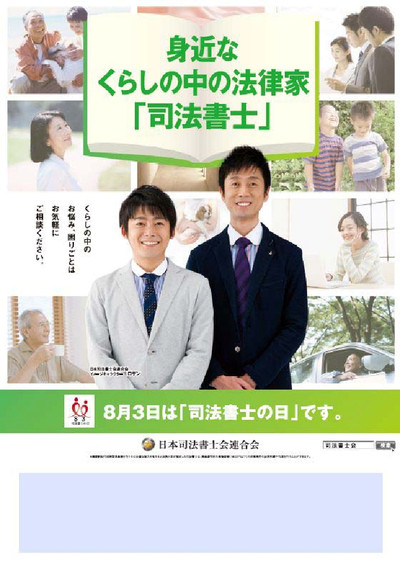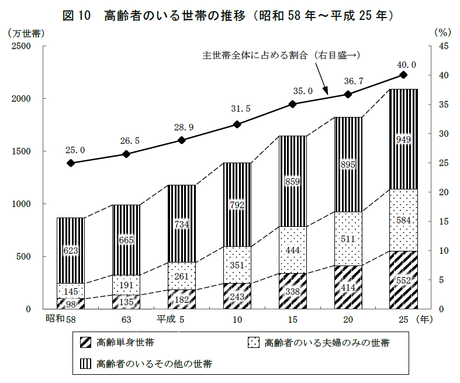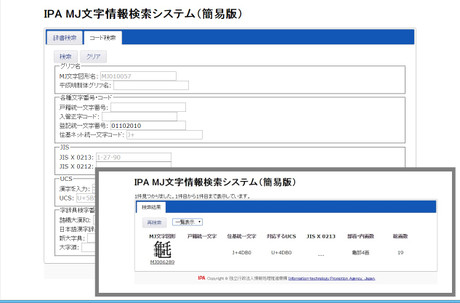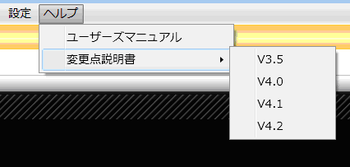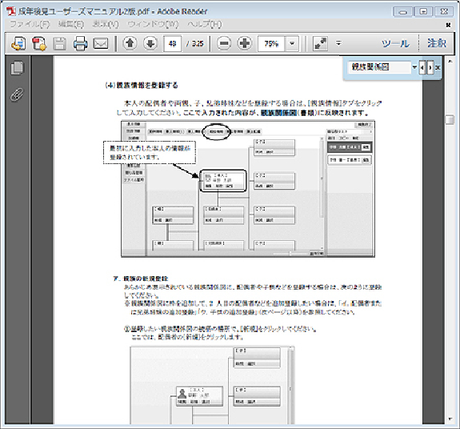甲州法度之次第
こんにちは、法務部の津田です。
先日まであんなに暑かったのに、気付いたらもう9月。月日が経つのがものすごく早い気がしますが、皆様いかがおすごしでしょうか。
私自身、ブログの順番が回ってくると、その時に気になる法律を毎回取り上げていましたが、今回は特に気になった法律がなかったので、過去の法をひとつ取り上げたいと思います。それは「甲州法度之次第」(こうしゅうはっとのしだい)です。
詳しい方はこのタイトルだけで誰が制定した法かすぐにおわかりでしょうし、わからなくても、「甲州」というタイトルから山梨に関する法であることが推測されると思いますが、これは戦国時代の武将である武田信玄が、(経緯は不明ですが)1547年6月に制定したとされる武田氏の分国法(各国独自の法)です。
全57か条からなるこの甲州法度之次第は、家臣に対する規律や統制、訴訟や治安の規定について定められており、末尾の条文には、当主である武田信玄自身についてもこの甲州法度に拘束されると記され、法度の主旨に反する言動に対しては身分を問わず訴訟を申し出ることが容認されているのが、他の多くの戦国時代の分国法とは違う点であると思います。その他、この分国法が特に有名なのは、17条で「喧嘩両成敗」を規定しており、喧嘩すること自体をけん制しているように見える点です。
私自身興味深いなと思うのは、27条で、子供が問題を起こした場合は成敗には及ばないが、13歳以後は咎められるとしている点で、現在の日本の刑法41条の責任年齢である14歳に比較的近いことから、当時の人の感覚も現代とそこまで変わらないのでは、と思える点です。また、40条が日本民法典を起草する際に参照されたとされており、それが現在の民法896条に影響を受けている点からも、現代の民法にもその爪痕を残しているのは、興味深い点でもあります。
多くの戦国大名が法とは名ばかりの家訓を残している中、具体的な訴訟についての規律や、当主自身を拘束する条文を広く領民に知らしめされていることからも戦国の分国法においては特異なものでり、武田家の徳治主義が如実にあらわれていると思われます。
わずか57条ですので、興味がある方は一度お読みになられてはいかかでしょうか。