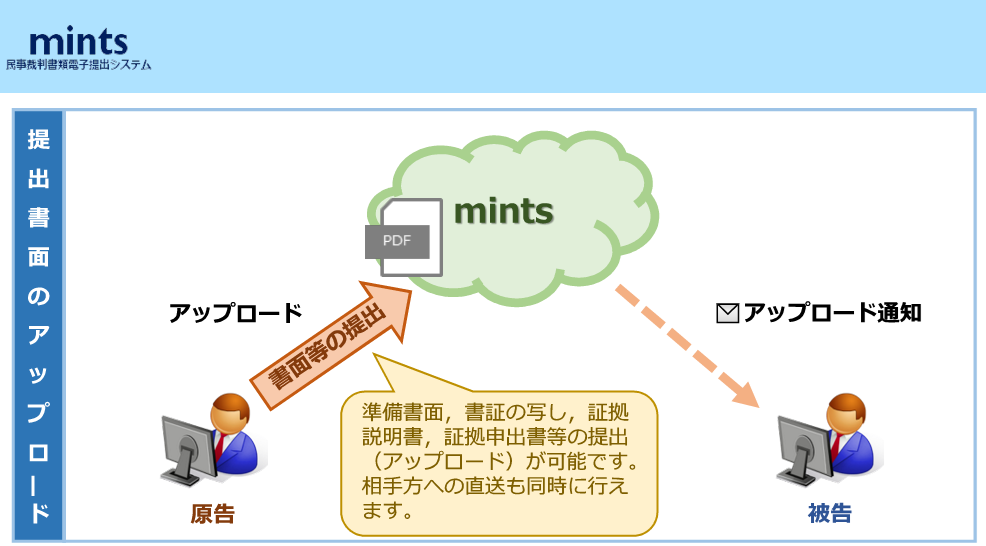春は忙しい季節?!
こんにちは、CSサポート部の山下です。
今年の冬は本当に寒かったですね。
日本海側や関東以北の方は、想像以上の雪に見舞われ、慣れている方でも大変だと毎日のニュースで拝見しておりました。
人一倍寒さに弱い私は、本社のある愛媛の冬でも十分寒かったですが、最近ようやく少し日差しが暖かい日がでてきてホッとしています。
ここ愛媛県松山市では「お椿さんまでは寒い」と昔から言われていまして、今年はお椿さんが2月23日から3日間でしたが、早いときは1月末か2月初めからと考えると、とても遅い開催日(遅くまで寒い?!)でした。
この「お椿さん」は伊予路に春を呼ぶお祭りとして、現在は、旧暦正月8日を例祭日として、その前後の3日間斎行されています。
全国各地から毎年約50万人の参詣者で3日間賑わいますが、参道の1.5キロほどは全面交通遮断され、その参道の両側には約800店の露店が立ち並び、初日の午前0時に大太鼓で開始を告げ、最終日の24時迄72時間行われます。松山市の人口が約50万人なので、人口と同じぐらいの人が参詣する愛媛では有名なお祭りです。
(伊豫豆比古命神社 -椿神社- https://tubaki.or.jp/)
年明けから寒いと言いつつあっという間に日が過ぎ、お椿さんも終わり、この春は司法書士実務にとって大転換というべき「特別委任方式」がはじまります。
もうすでにいろいろ勉強されている先生方もいらっしゃると思いますが、「特別委任方式」は、司法書士が登記義務者から「特別の委任」を受け、一定の要件を満たせば司法書士自身の電子署名のみで「登記原因証明情報」を作成・オンライン送信できる仕組みです。
一定の要件としては、以下のようになります。
1.登記義務者から司法書士に対し、登記原因証明情報作成について特別に委任されていること
2.司法書士自らが登記原因証明情報を作成し、そこに司法書士本人の電子署名を付すこと
3.司法書士が契約締結や代金決済といった場面等で厳格に事実確認を行ったことを、登記原因証明情報の中に記載すること
4.登記原因証明情報を作成した司法書士自身が、その登記申請の代理人であること
5.登記申請書に、「特別委任方式による申請である旨」を記録すること
6.登録免許税は電子納付で行うこと
司法書士システム権は特別委任方式に合わせた登記原因証明情報の書式や、委任状書式を追加して皆様のお仕事をサポートさせていただきます。
これからも引き続きよろしくお願いいたします。