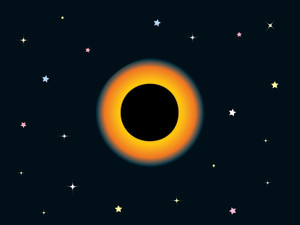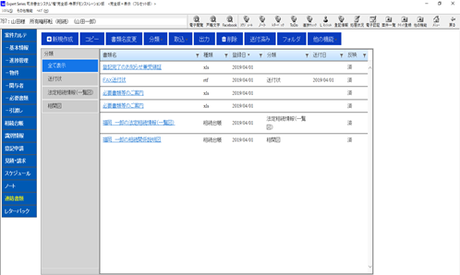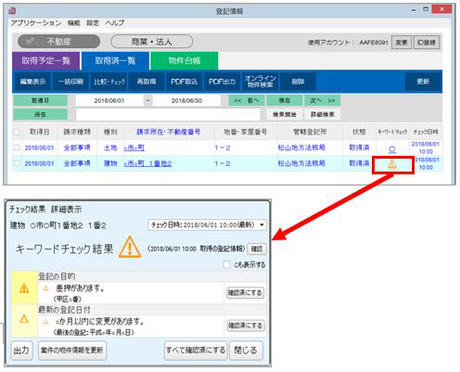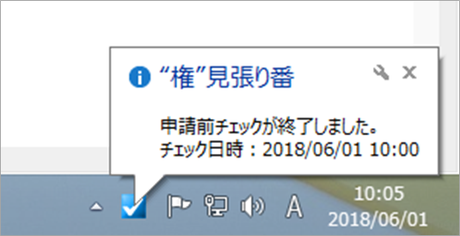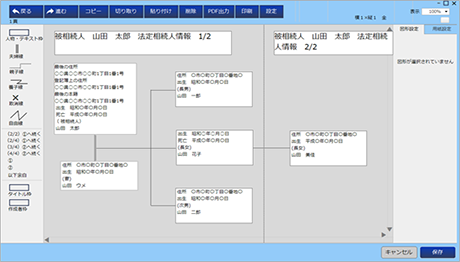スマートホーム化への挑戦!
こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。
今年のゴールデンウィークは過去最長の連休でしたが、みなさまはいかがお過ごしだったでしょうか?
我が家では、家でゆっくりと過ごそうということになり(単に手配に乗り遅れたということもありますが…汗)、主に近場でショッピングや外食をしたほか、普段はできない事にも挑戦をしました。
「普段はできない事に挑戦」というと少し大げさかもしれませんが、私は以前からスマートスピーカーとスマートホーム化に興味をもってまして、我が家に導入するには時間とお金と家族の理解が必要ということでずっとチャンスをうかがっていたのですが、今回の連休で実現ができましたのでその話をしたいと思います。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、「スマートスピーカー」とは、今日の天気やニュースなどを言葉で話しかけると音声で答えてくれたり、音楽をリクエストすると音楽をかけてくれるなどのAI機能を搭載したスピーカーです。googleやamazonが販売しているものが有名です。これと特定の機材を組み合わせて利用すると、テレビやエアコン、ライトなどの家電をリモコンを使わずに音声だけで操作できるようになります。例えば、「テレビをつけて」と話しかけるとテレビの電源が入ったり、「おやすみ」と話しかけるとリビングのテレビとエアコンとライトを一斉に消してくれるといった事ができるわけです。
さらに、音声操作だけでなくスマートホンと連携させれば、外出先から家電を操作したり、家の近くに帰ってくるだけでリビングのライトやエアコンの電源を自動で入れるなんてこともできます。このように家電などを一括で管理するのがスマートホームです。
今回はリビングの複数家電と玄関のカギを音声やスマホで一括管理をすることを目標にして、必要機材を購入したところ、おこずかいの範囲を超える約3万円の買い物になりました。家族からはわざわざ面倒なことをしなくても今まで通りでいいのでは?という意見もありましたが、子供が小さい頃から最先端の技術に触れさせておいた方が将来の役に立つという必殺の呪文を唱えて購入しました(笑)。
実際に導入した結果は、音声操作には言い方のコツが必要であったり、思った通りに家電を動かす事ができない事柄があったり、ときどき原因不明で動かないことがあったりで信用して利用するにはもう一歩な感じですが、自分としては概ね満足できるレベルでした。特にどのような言葉で発声すると家族全員が操作しやすいか?を考えたり、寝る前や起きた時に一斉に操作する家電と一緒にアナウンスしてほしい情報の組合せや順番はどれか?とかをあれこれ考えて動作させるのはとても楽しい作業でした。
導入直後の試行錯誤中は家族へ変更の周知を忘れてクレームが出たりもありましたが、妻は料理中の音声キッチンタイマーのセットが気に入り、娘は名前を尋ねると自分の名前を答えてくれるのが楽しかったようで良かったです。
もし導入を検討されている方は(参考にならないかもしれませんが)一つの例として参考にしていただければ幸いです。