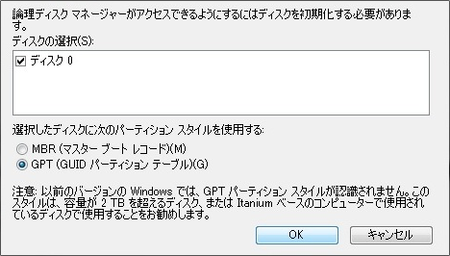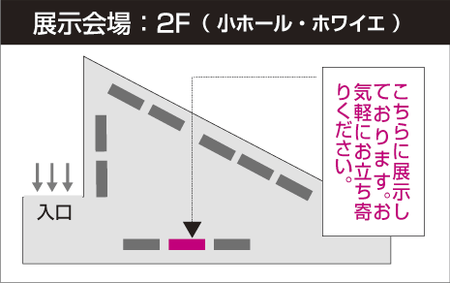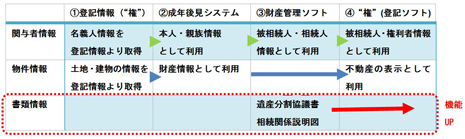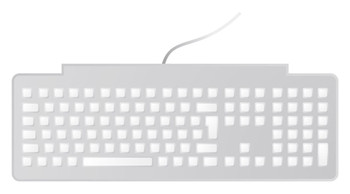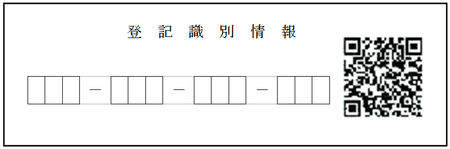こんにちは、法務部の津田です。
今回は私が注目している、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の改正について紹介したいと思います。
パート・有期・派遣等のいわゆる非正規雇用労働者の割合は、2003年には30.4%にまで増加したものの正規雇用労働者に比べて処遇が低く、その処遇格差が社会問題視されてきました。そのため、2007年にはパートタイム労働法の改正によって、パート労働者への差別を禁止する規定が設けられ、2012年には有期契約労働者・無期契約労働者間の不合理な動労条件の相違を禁止する規定が労働契約法に導入されました。しかし、2013年時点での正社員と正社員以外の者の賃金の格差は時給にすると約700円~900円であり、非正規雇用労働者の割合は36.7%にまで上昇しています。このような状況下で、パートタイム労働法のさらなる改正が平成2014年4月23日に公布され、2015年4月1日から施行されます。
正社員と差別的取扱いが禁止されるパート労働者について、改正前は、
①業務の内容及び当該業務に伴う責任の限度(職務の内容)が通常の労働者(正社員)と同一であること。
②当該職務の内容及び配置の変更の範囲が通常の労働者と同一と見込まれること。
③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること
と規定されていました。
今回の改正では、上記①、②に該当さえすれば、有期労働契約を締結しているパート労働者でも正社員との差別的取扱いが禁止されています。
「短時間労働者の待遇の原則」の新設
雇用するパート労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする待遇の原則の規定が創設されています。 改正後は、パート労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パート労働者の雇用管理の改善を図る必要があると思われます。
「事業主がパートタイム労働者を雇用したときの説明義務」の新設
今回の改正ではパート労働者の雇用時に、事業主は実施する雇用管理の改善措置の内容について説明義務を負うことになりました。
この雇用管理の改善措置の内容の例としては
・賃金制度の説明
・どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか
・正社員へ転換することができるか
などがあげられます。これまでも説明義務は存在していましたが、パート労働者が求めた場合に限られていたのを、義務としたものです。
「パート労働者からの相談に対応するための体制整備の義務」の新設
今回の改正によって、今後、事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないとされました。 この相談に対応するための体制整備の例としては
・相談担当者を決め、相談に対応させる
・事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う
等が考えられ、企業としては、パート労働者の相談に応じる窓口となる部署を文書で周知する必要もあります。改正の履行強化の仕組みとして、これらの規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をしたにもかかわらず事業主がこれに従わない場合には、その事業主名を公表することができる規定も創設されました。
以上がパートタイム労働法の改正ですが、パート労働者が就労していることが多いと思われる企業に今回の改正によって、どれほどの影響を与えるか、注目してみていきたいと思います。