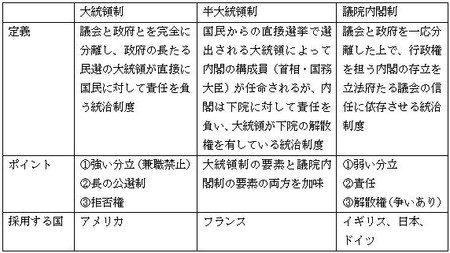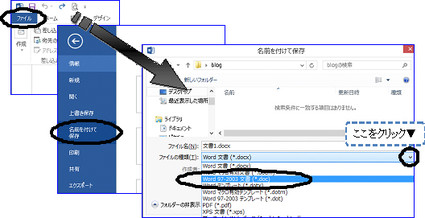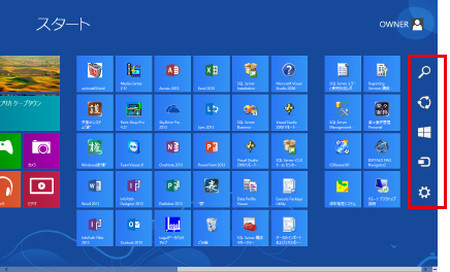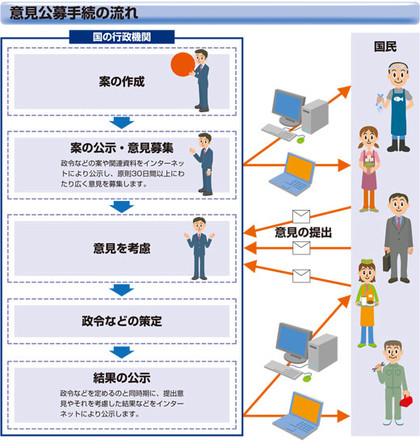お・も・い・や・り
システムサポート部の村上です。
昨秋、“権”ユーザの皆様を対象にアンケートを実施し、いろいろなお声を頂きました。その声をもとに、より充実したサポートをめざし、外部から講師をお招きしてホスピタリティ研修を行いました。
研修の中では、どのように業務に取り組むかといったところから、感情のコントロールを行うことの大切さ、視点の位置の重要性など1日で盛りだくさんの内容を学びました。
中でもおもしろかったのが「わらじ物語」。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、簡単に内容を説明しますと・・・
武士が商家の娘と駆け落ちをして浪人となり、職を転々とします。わらじを作って店に卸しますが、そのわらじが非常に丈夫でなかなか壊れません。店の番頭は「もっと弱く作れ」といいます。浪人が飲み屋で愚痴をこぼすと店主が「そのまま頑張りなさい」と励まします。しかし、浪人はわらじ作りを辞め人夫として働き始めました。一所懸命仕事をしますが、同僚から「もっとゆっくり仕事をしてくれ」と頼まれます。浪人は村の長老に相談しますが「そんな話は聞きたくない」と言われました。自宅に帰ると、妻が「愛しています」と書き置きを残して、実家に行ってしまいました。浪人・妻・番頭・店主・人夫、長老のうち、あなたは、誰が一番悪いと思いますか?
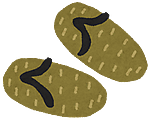
といった問題に対して、順位付けをして数人で検討を行います。
順位に「正解」があるわけではありませんが、いろんな立場でいろんな視点で考えることで、様々な意見が出てきて非常におもしろかったです。
ホスピタリティを考えたときに、どの立場に立って考え、状況を把握し、何をどうするのがいいのかを判断することが非常に大切になります。非常に難しいことではありますが、今後も研修の内容を忘れないように取り組んで行きたいと思います。
今後の対応の中で、お客様に少しでも「おもいやり」の気持ちが届けられるように努力していきたいと思います。システムサポート部の対応を楽しみにしていてください。今年のアンケートに、その成果が反映されればいいなぁ。。。