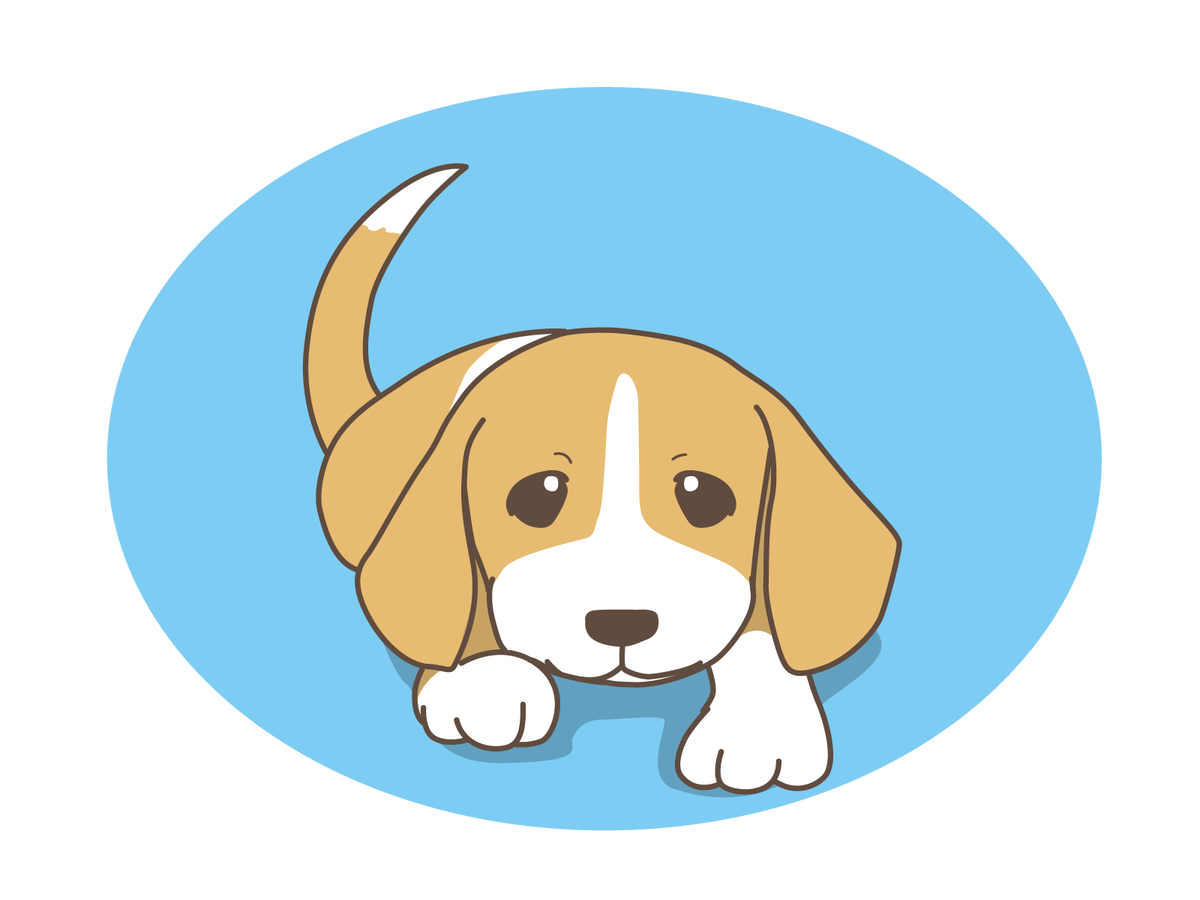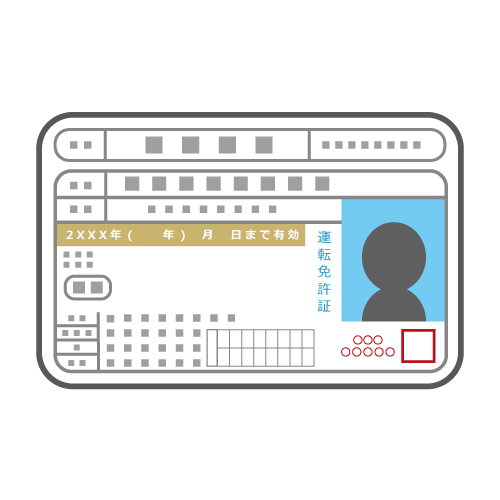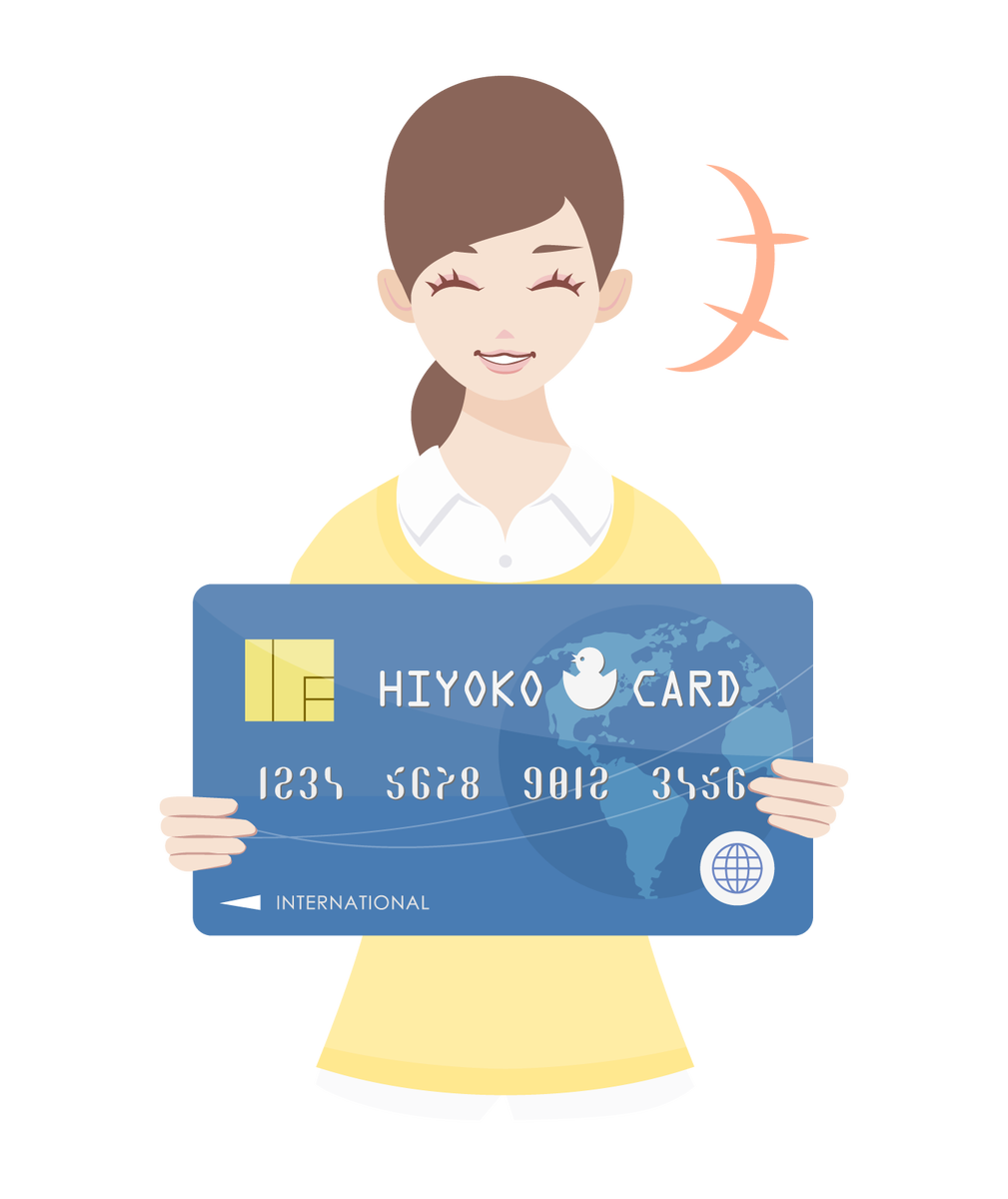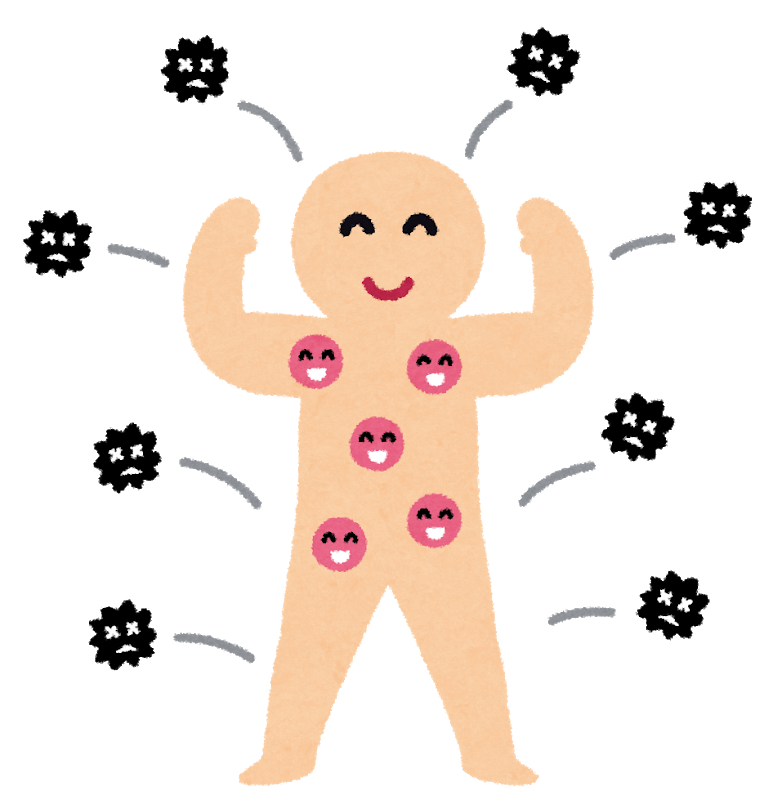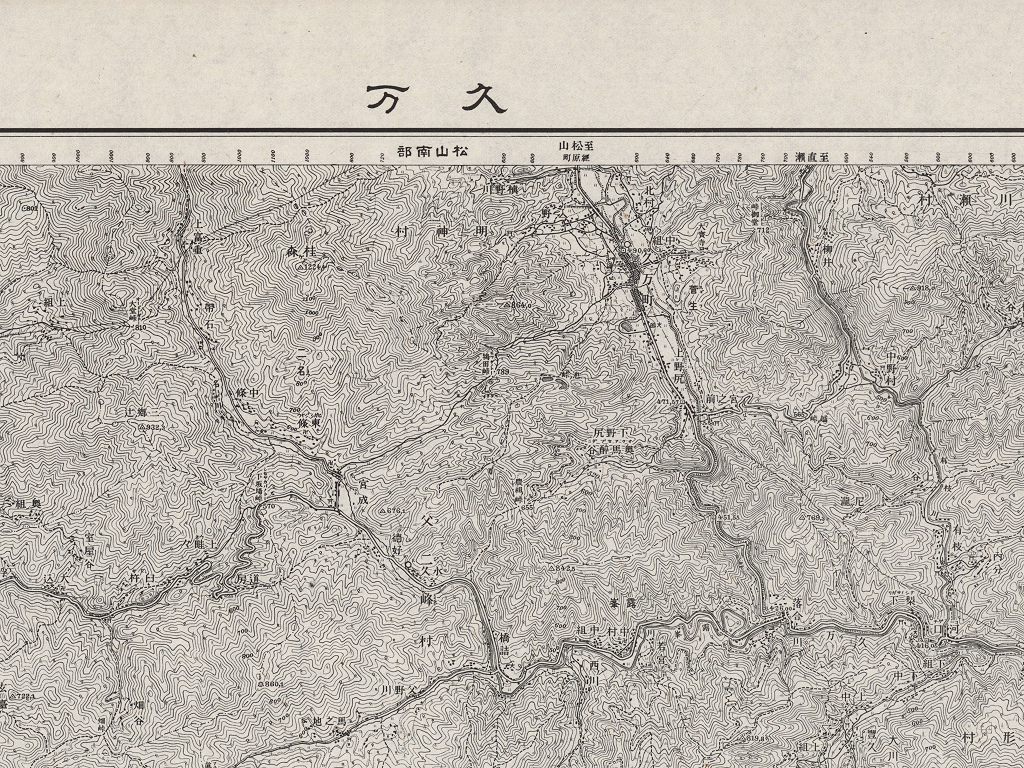こんにちは。総務部の大内です。
8月に入り夏本番となりましたが、皆様お盆休みの予定はお決まりでしょうか?お盆休みはまだですが、私は先日の連休に日本のスイスといわれる四国カルストに行ってきました。景色がきれいで涼しく、気分がリフレッシュできましたので皆様にも写真でお裾分けします!
最近、以前よりも「動線」を意識するようになりました。きっかけは家族に頼まれてキッチン下の引き出し収納を片付けたことでした。片付けをしたのは鍋やフライパンをしまっていた引き出しで、我が家は鍋が多めなので引き出しの中がかなり窮屈でした。たくさんの鍋をサイズ順に重ねて収納してあったため、鍋を使うには、引き出しを開け、上の鍋を持ち上げ、目当ての鍋を取り、上にあった鍋を戻し、引き出しを閉め……という手順が毎回生じており、料理にたどり着くまでの手数が意外と多く感じました。そこで、鍋を横に寝かせて重ねる収納ではなく、引き出しの中に仕切りを作って鍋を立てて並べる収納に変更したところ、引き出しの手前がよく使う鍋になるようにしました。これで引き出しを開けたらすぐに目当ての鍋を取り出して使えるようになり、使うつもりのない鍋を触る必要がなくなったので、以前よりも衛生的です。
この片付けをして以来、会社の自分の机や引き出し、デスクトップのショートカットなどを、より自分の動線に沿って使いやすく・ムダなく・わかりやすい配置にできないかと考えるようになりました。机よりも右側の通路を通ることが多いので右足のまわりにはものを置かない、パソコン本体が左側にあるからZoomミーティングが始めやすいようにイヤホンは左側にしまう、電話対応中によくみるマニュアルは引き出しではなく机上のファイルボックスへ、頻繁にご案内する"権"の新着情報ページはブラウザにピン留めをする……などなど。一つ一つは小さな事柄ですが、これらの積み重ねにより生活や仕事中のちょっとしたストレスや手間が減らしていけそうです。
動線を意識するようになってもう一つ自分の中で変化したのが電話対応です。
お問い合わせの多い「電子認証キット」のご案内をする際、以前は複雑な状況であればあるほど私が自分で説明しやすい順序でご案内してしまうことがあったのですが、今はお客様の動線を意識したご案内をするように心がけています。お客様の動線を意識することにより、設定確認などの二度手間を減らすことができ、結果的に対応時間を短縮できて、お客様も問題を早く解決できそう&私もほかの業務に使える時間が増えそうです。
また、私個人の話ではありませんが、総務部では最近、商品やカタログなどの在庫、書類などの保管場所の大幅なレイアウト変更を行いました。出荷作業場所の近くに商品在庫を置き、普段取り出さない契約書や請求書の在庫は別の部屋へ、古くてもう使わないマニュアルなどは倉庫へ移すことでスペースにゆとりのあるレイアウトに生まれ変わりました。また動線を意識した変更を行ったことで仕事がしやすくなり、余裕を持たせた配置にしたことで在庫も見やすくなりました。
更に以前は休憩スペースも在庫や書類に囲まれてすこし窮屈な雰囲気だったのですが、古いマニュアルたちが撤去されたことで以前より広くなったため落ち着いて休憩できるようになり、「動線」にありがたみを感じつつ紅茶をいただくちょっと優雅な昼休みを過ごせるようになりました(笑)ちなみに夏の暑さストレスには、冷たくて香りも良いアイスティーをオススメします♪
水分補給はお水やスポーツドリンクなどで、熱中症には十二分に気を付けてお過ごしください!