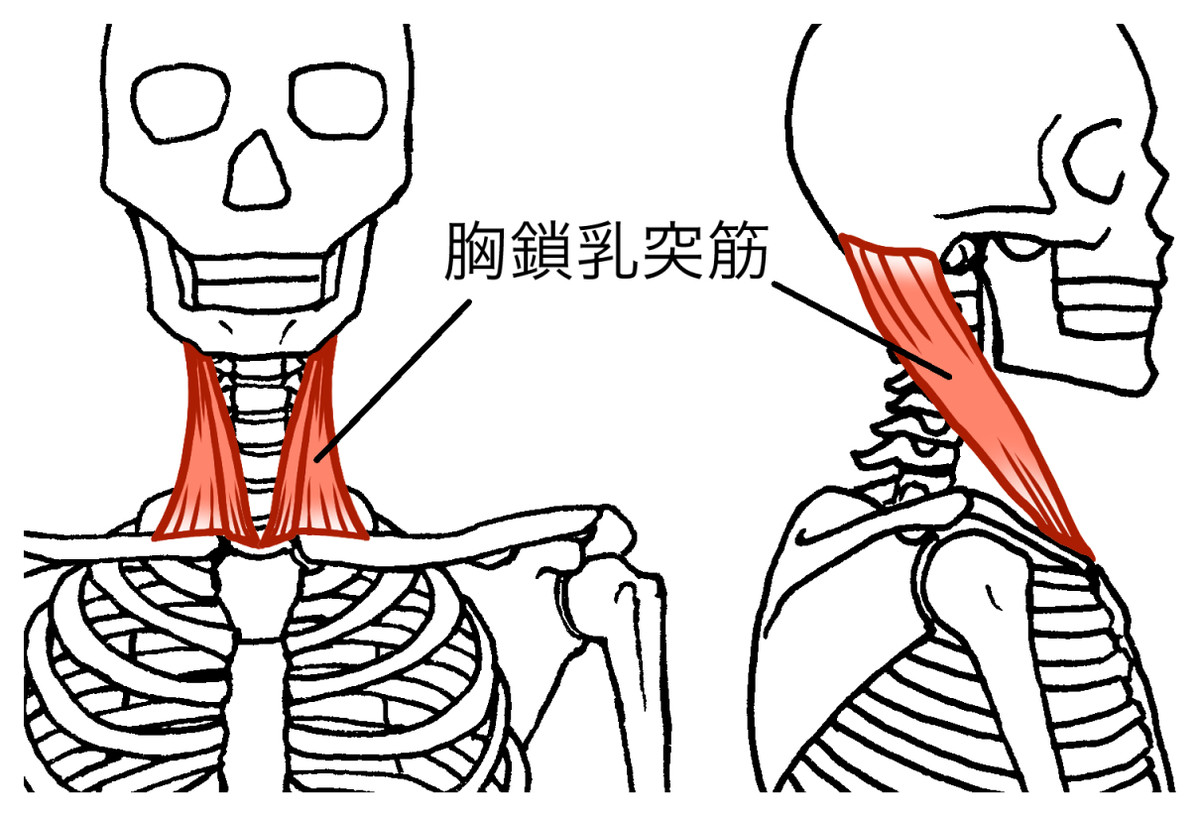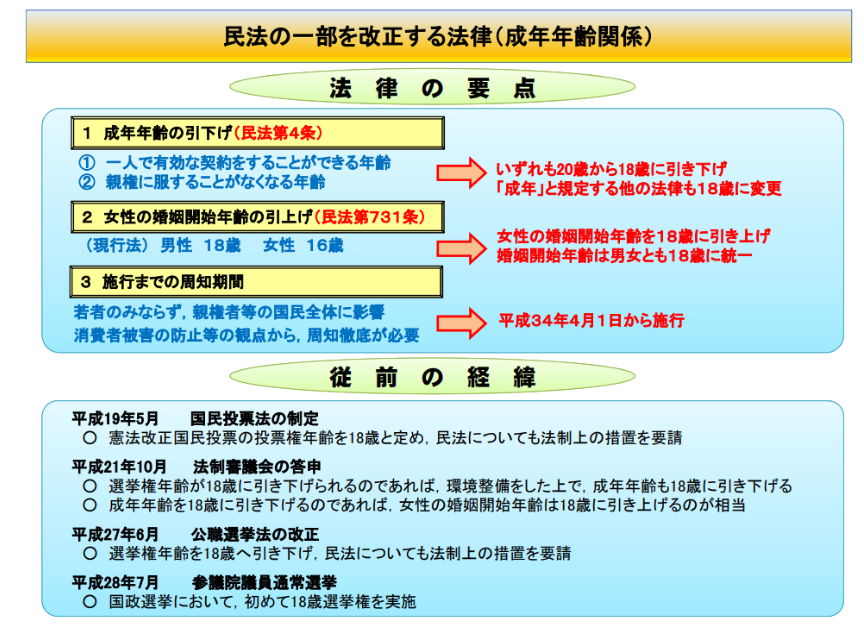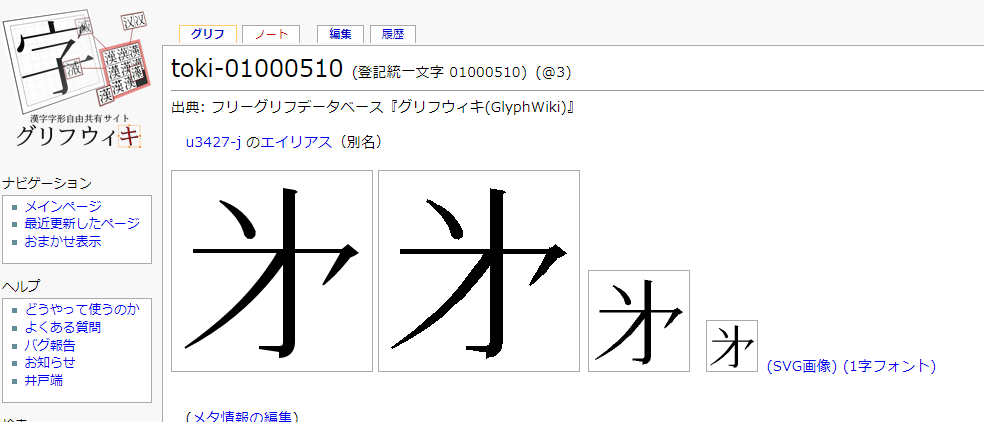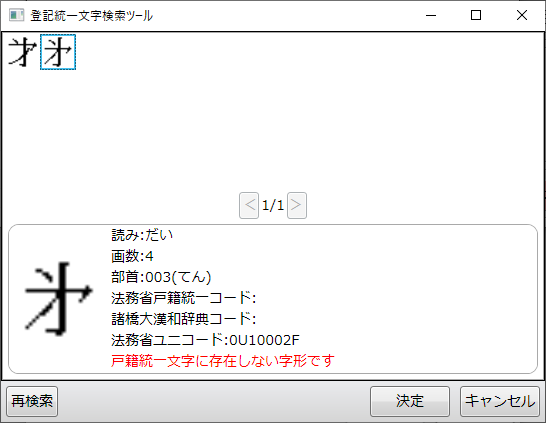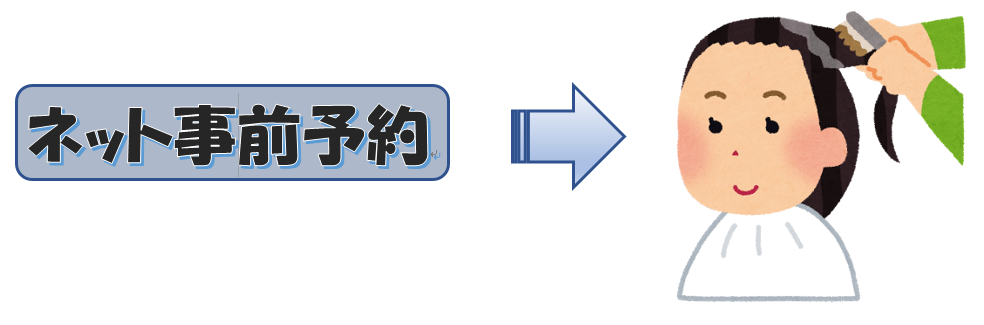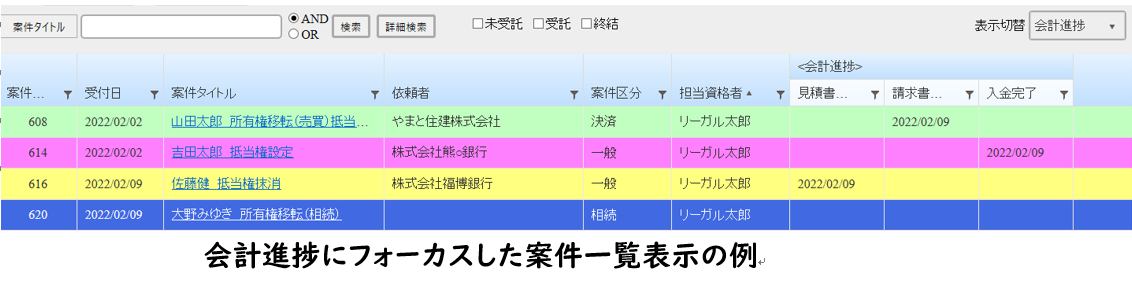GIGAスクール構想がやってきた
こんにちは、イノベーション開発部の大西です。
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、もっとも大きな影響を受けた分野の1つが学校教育だと思います。
我が家の3人の子供たちも、2020年3月の突然な臨時休校に始まって現在に至るまで、日々の学校生活から各種行事まであらゆる活動について、それ以前にはなかった様々な制限を受けながら、それでも日々頑張って元気に過ごしております。
さて、そんなコロナ禍の下、昨年2021年の春に中学生になった長女が、学校から唐突にタブレット端末を渡されたかと思うと、それから少し遅れて夏頃には、小学生の息子たちも全く同じような端末を1人1台ずつ持って帰ってきました。
それ以来子供たちは、この「GIGAスクール構想」とシールが張られたタブレット端末を学校と自宅の間で持ち運び、タブレット端末上で出された課題に取り組むようになりました。
この「GIGAスクール構想」という言葉、皆さんもどこかで一度は耳にしたことがあるかと思いますが、ではその内容についてはどのようなものなのでしょうか。これは2019年(令和元年)に文部科学省により開始された、全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備することを目的とした取り組みのことを指します。
2019年当時に先進諸国と比べてICT方面で遅れをとっていた日本の教育環境を改善することを目的としており、当初5年間かけて順次整備が進められる予定でしたが、新型コロナの感染拡大を受けてスケジュールが前倒しになった結果、2021年中には小中学生1人に1台のコンピューター配備がほぼ完了したそうです。
ちなみに名称にある「GIGA」は「ギガ」と読みますが、これは数の単位で用いられるギガ(10の9乗=10億)ではなく、「Global and Innovation Gateway for All(全ての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉)」の略称だそうです。
子供たちのタブレット端末を自宅Wi-Fiに接続する際に、私も少し実際に触れてみたのですが、中身は普通のWindows 10を搭載したPCでした。マシンスペック的には高い性能とは言えないものの、Webサイトの閲覧や動画再生などは特に問題なく使えるようです。
さてこのタブレット端末を実際どのように使っているかについてですが、例えば先日小学2年生の息子が取り組んでいた宿題は、おおよそ以下のような内容でした。
1.国語の教科書の音読をタブレット端末に録音する。
2.録音した音声データを自宅のネット回線経由で先生宛にアップロードする。
…上記の例はちょっと「とりあえず試しにやってみた感」が強すぎるかもしれません。それはともかく、現在のところは既存の紙と鉛筆を使った学習内容については従来とあまり変わらないようですが、今後色々な教科書やノートがタブレットにまとまることで、子どものランドセルなど少しでも負担が軽くなればいいですね。
さすがに「学校と自宅を繋いだオンライン授業の実施」となると、いろいろハードルが高く早期実現は難しいかも知れません。
今後はもう少しICTの有効活用を進めていただいて、「これぞまさに革新的」と思えるような学習環境が実現されるよう、今後の「GIGAスクール構想」に期待したいと思います。
―以上―