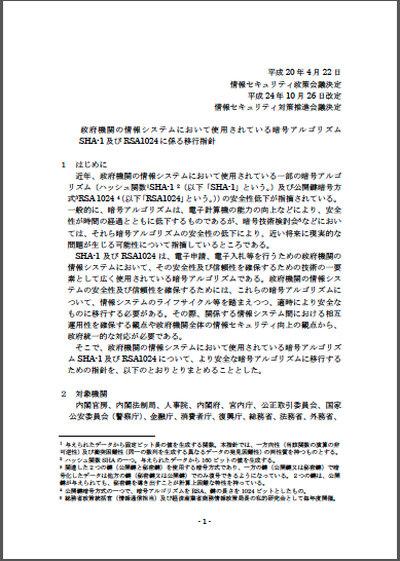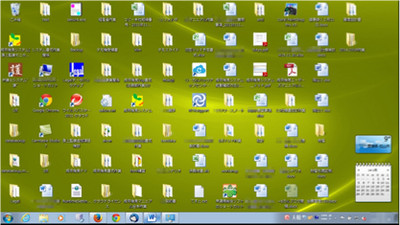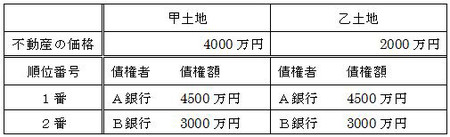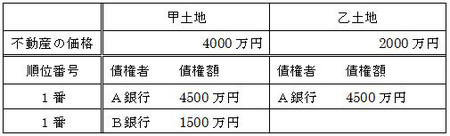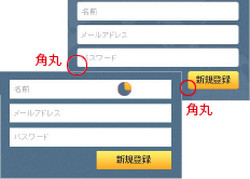リーガル・カルテについて
こんにちは。開発部の橋村です。
先日、リーガル・カルテが発売になりました。このソフトの開発にあたっては、開発部全員はもとより、大勢の他部署のスタッフを加えて、文字通りの総力戦でしたので、関わった者の一人として、リリースの日を迎えて非常に感慨深いものがあります。さて、そのリーガル・カルテでは、大きく2つの点を目標に開発を進めて参りました。
■目標その1:先生方と依頼者様の連絡を円滑にすること
顧客管理、と一口に言ってしまうといわゆる住所録が頭に浮かびますが、氏名・住所・連絡先等の基本情報に加え、
・どういう経緯で事務所に依頼してくる運びになったのか、
・面談や電話連絡等でどんなお話をしたのか、
・送付した書類、受領した書類はどんなものか。
・その顧客特有の事情はなにか。
こういった情報を登録しておいて、顧客との関係をスムーズにしようという取り組みのことをいいます。
近年、司法書士事務所様の業務が多様化する中、特に成年後見・相続等の分野において個人依頼者様との関わりを、より密にしていきたいというお声をいただく契機が多くなって参りました。
リーガル・カルテでは、依頼者様のカルテに基本情報を登録し、何かのアクションがあるごとに履歴をカルテに追記していくことで、誰が、いつ、どのような対応をしたのか履歴を一覧できるようになっております。
単なる名簿連絡先管理ではない、+αの情報を加え、依頼者様に対する、よりきめ細かいサービスのご提供、さらには、先生と事務所スタッフの皆様の間の連絡漏れ防止などにもお役立て頂けると、大変嬉しく思います。
■目標その2:リーガル製品を横断的に運用すること
リーガルでは、登記・裁判・成年後見など、各分野に特化した製品をリリースして参りました。一方で、複数の業務分野を横断するような事案については製品を切り替えながら対応しなければならず、データの二度打ちが必要になったり、頻繁にソフトの起動や終了をおこなったりする必要があり、
煩雑だ、というお声を頂いておりました。
リーガル・カルテでは、依頼者様のカルテを介して、リーガル製ソフトを呼び出して利用できます。例えば、成年後見ソフトウェアで打ち込んだデータを権の登記書類作成に利用する、などのデータ連係が可能です。
まだまだ対応分野は少ないのですが、「登記情報の閲覧機能を成年後見や財産管理で利用できればいいのに」「成年後見の親族図を登記に利用できればいいのに」といったご要望に対して、順次対応していきたいと考えております。
また、リーガル製ソフトに登録したデータは、カルテからは業務対応履歴として一覧することができますので、目標その1:で挙げた対応履歴の管理と完全に統合して、依頼者様との円滑なやり取りにお役立て頂けます。
■今後
現在、リーガル・カルテは2回目のリリースを行ったところです。初版では権と成年後見システムの連動が、第2版では財産管理ソフトウェアと任意売却ソフトウェアの連携がサポートされました。近々、大規模なネットワークでの運用に対応した第3版をリリースする予定です。
引き続き、第4版、第5版・・・と、連携対応ソフトを拡充していくとともに、使い勝手の向上に努めて参りたいと考えております。より多くの方に使って頂きたいので、現在は特別に無償でダウンロード・利用ができるようになっております。一度お試しのうえ、ご意見・ご感想などお寄せいただけると幸いに存じます。