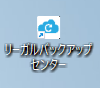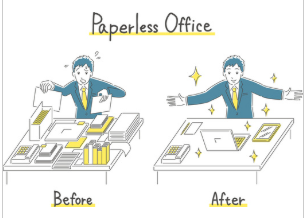子供へのSNS規制はどうなるのか
こんにちは、イノベーション開発部の津田です。寒い季節がやってきましたが、皆様いかがおすごしでしょうか。
さて、今回の記事ですが、法律関連で興味深かったものとして、つい先日発表されたオーストラリアの「16歳未満のSNS利用禁止」規制について触れたいと思います。。
昨今SNSの影響は大きく、子供たちの多くがSNSを使用する中、その悪影響も騒がれていましたが、ついに全面的に禁止する国がでてきたな~というのが、第一感想でした。
この規制で利用が禁止となったのは、TikTok、X、Facebook、Instagram、YouTube、Snapchat、Threads等の大手SNSサイトで、主な禁止基準として、
・プラットフォームの重要な目的が2 人以上のユーザー間のオンラインソーシャルインタラクションを可能にすることであるかどうか
・ユーザーが他の一部のユーザー、または全員とやり取りできるかどうか
・ユーザーがコンテンツを投稿できるかどうか
があり、YouTube Kids、Google Classroom、WhatsApp等はその基準を満たさないと判断されたため対象外とされたものの、基本的には大半の大手SNSサイトが禁止となりました。
また、罰則についてですが、違反したとしても、子供や親は処罰されず、代わりにソーシャルメディア企業に重大な違反や度重なる違反がある場合に、最高4,950万豪ドル(3,200万米ドル、2,500万ポンド)の罰金を科せられることになります。
以上がざっくりした規制の内容なのですが、はっきりいってどこまで効果があるのか疑問です。悪事を働く人たちは必ず法の抜け穴を探しますし、規制してもどこまで効果があるのかわかりません。そもそも規制よりもSNSの危険性をもっと学校等で教えていくべきでは?とも思ったりします。罰則についても、元Facebook社幹部のスティーブン・シェーラー氏はAAP通信に語ったこととして、「メタ社が5000万豪ドルの収益を上げるのに約1時間52分かかる」ということからも、違反しても罰則の効果が薄いのでは?とも思います。
また、こういった規制により懸念されるのは、ユーザーの年齢確認に必要なデータの大規模な収集と保管がこれまで以上に行われる懸念はないのかと思いますが、規制の方が優先という現状があります。
こういった規制に関して、諸外国の動向に関しても興味をもったので調べると、デンマーク、ノルウェー、フランスは15歳未満のSNSの使用禁止を計画しており、スペインでは、16歳未満の子供のSNSのアクセスには法定後見人の許可を義務付ける法案を起草したりしています。一方、米国ユタ州では、18歳未満の子供が親の同意なしにSNSを利用することを禁止する試みが2024年に連邦判事によって阻止された例がありますが、やはり規制を試みようとしています。
この規制の流れが日本について飛び火するかわかりませんが、諸外国のプレッシャーに負けて規制に傾くにせよ、是非とも慎重に判断していただきたいものです。特に日本という国は、一度法律ができてしまうと廃止するのはかなり難しいので、十分な検討をする必要があると思います。
今となっては10歳から15歳までの子供のうち96%が何らかのSNSを使用しているとの統計があるとのことで、利用自体をさまたげるのはなかなか難しいと思いますので、上記でも少し述べましたが、規制するよりも、SNSの危険性をもっと学校等で教えていく方がより効果的で、上手に付き合っていくべきでは?と個人的思ったりしますが、はたしてどうなるのやら・・・・今後の動向について興味深く見守っていきたいと思います。